「学校の制服や体操服を着たがらない」「朝、着替えで大泣きする」そんなお子さんに悩む保護者の方は少なくありません。ただのわがまま?甘え?そう感じるかもしれませんが、発達障害や感覚の特性が背景にある場合、適切な理解と対応がとても大切です。
考えられる原因とは?
- 感覚過敏(触覚の過敏)
発達障害のある子に多いのが、「感覚過敏」です。制服や体操服の素材・縫い目・タグ・ゴムの締め付けなどに対して、一般の人には感じにくい不快感や痛みを感じてしまいます。
例:
• ポロシャツの襟がチクチクして不快
• ズボンのウエストゴムが苦しくて泣いてしまう
• 靴下の縫い目が気になって履けない
- 見通しが持てない・急な変化への不安(ASD傾向)
制服や体操服に着替えるという“場面の切り替え”が苦手で、「いつ」「どこで」「なぜ」着替えるのかが曖昧だと不安になって動けなくなることがあります。
例:
• 朝の着替えルーティンが崩れると混乱
• 「体操の時間に体操服を着る」という意味が曖昧
- 手先の不器用さ・身体の不器用さ(発達性協調運動障害)
ボタンが留められない、ズボンが上手く履けない、袖に腕が通せないなど、運動の不器用さから“着たくても着られない”場合もあります。
例:
• ボタンをうまく留められず、着替えに時間がかかる
• 前後ろがわからなくなる
保護者ができる対処法
- 着られる素材・服を工夫する
• タグを取る、裏返して着る、柔らかい素材を使うなどして負担を軽減
• 肌触りの良いインナーを制服の下に着る
• ゴムを緩めに調整する、ウエストを紐で調整できるタイプを選ぶ
ポイント:
感覚過敏の子にとって、素材は「痛み」にもなります。肌触りの良い素材で“着られる感覚”を育ててあげましょう。
- 練習の「場所」と「時間」を整える
• 朝のあわただしい時間ではなく、余裕のある時間におうちで練習
• 学校ごっこなどで遊びの中に取り入れると抵抗が少なくなります
ポイント:
「今は練習だから失敗しても大丈夫」という安心感が大事です。
- 手順を可視化する(視覚支援)
• 着替えの順番をイラストや写真で並べて示す
• 「何を」「いつ」「どうやって」着るのかを、目で見て理解できるようにする
ポイント:
見通しがあることで不安が減り、着替えに前向きになれます。
- 着替えやすい服を選ぶ・学校に相談する
• 無理に制服を着せず、まずは似た形で“着られる服”を探しましょう
• 学校側と連携し、無理のない範囲で着替えられるよう工夫してもらうことも大切です
例:
• 上着だけ制服にする
• 体育の授業は無地のTシャツとハーフパンツにする など
まとめ
「着たくない」ではなく「着られない」かも
「どうして着ないの!?」と言いたくなることもあると思います。でも、その子にとっては、服を着ること自体が“ストレス”や“苦痛”になっている可能性があります。
着ることを強いる前に、「どんなことがつらいのかな?」「どうしたら楽になるかな?」と、一緒に原因を探してあげてください。「その子なりの理由」があり、寄り添うことで乗り越えられることがたくさんあります。
大切なのは、「着られた!」という小さな成功体験を積み重ねること。焦らず、その子のペースで一歩ずつ進めていけるとよいですね。
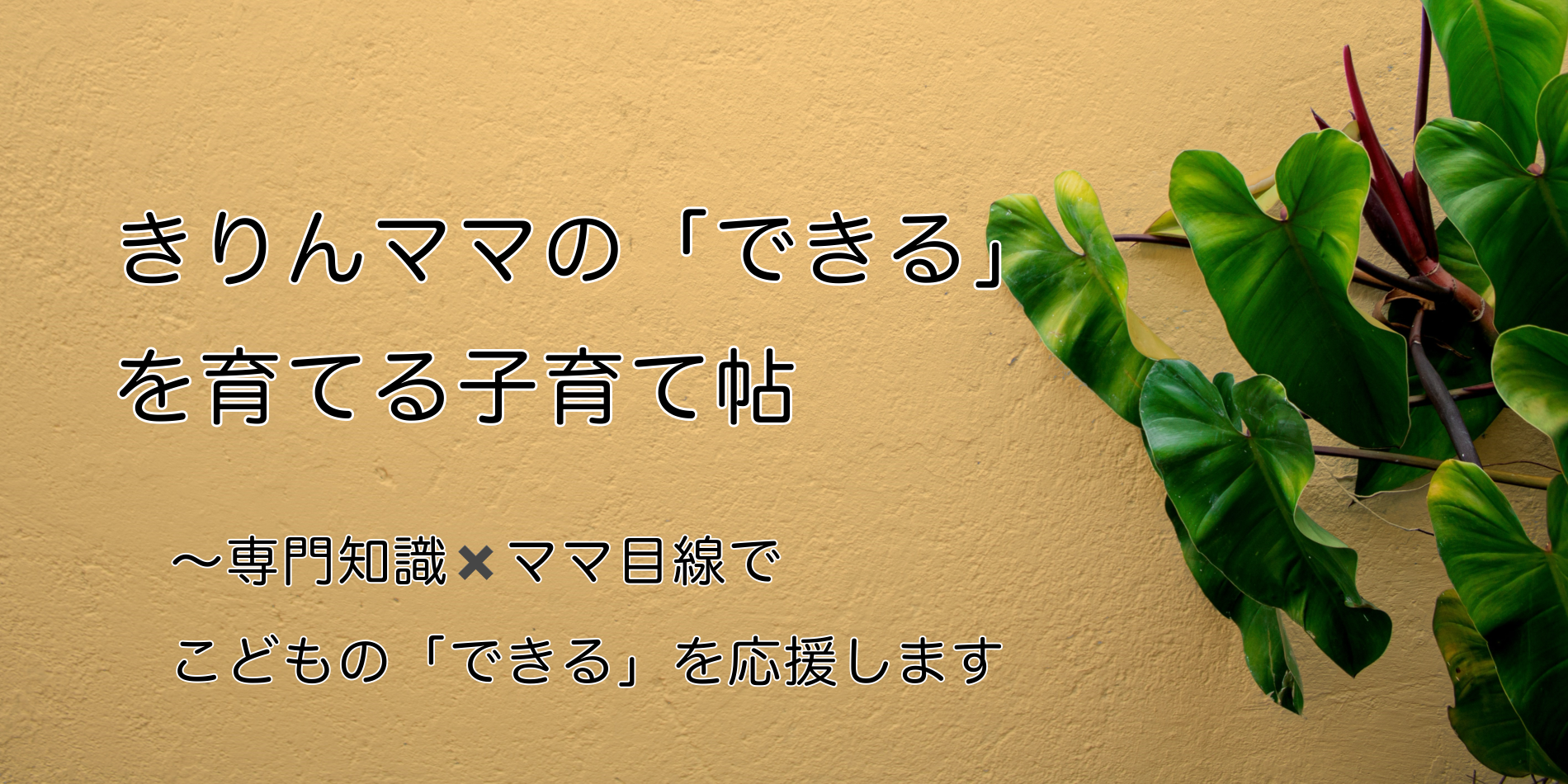
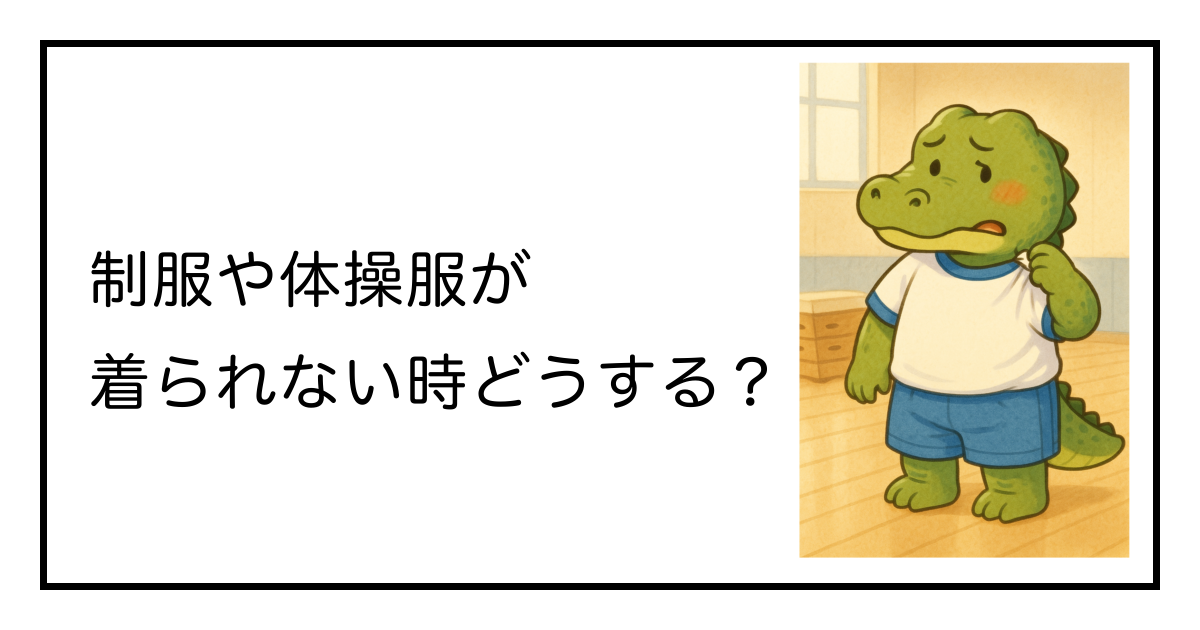
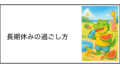
コメント