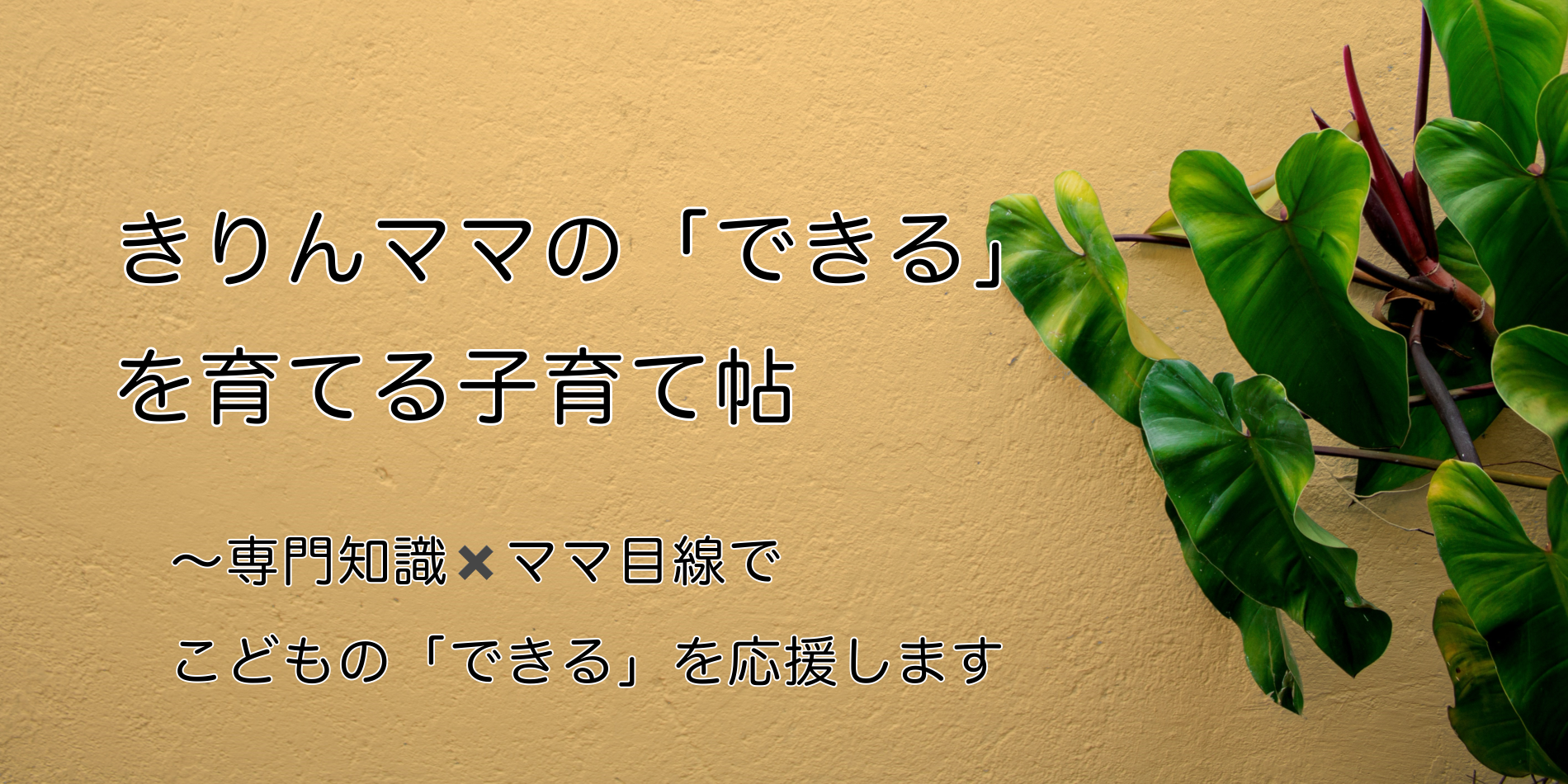子どもの「できる」を引き出す土台づくり
みなさんは「感覚統合(かんかくとうごう)」という言葉を聞いたことがありますか?
少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は子育てにとってとても大切な考え方なんです。
感覚って、何のこと?
人は毎日、たくさんの「感覚」を使って生活しています。たとえば…
• 目で見る(視覚)
• 耳で聞く(聴覚)
• 手で触る(触覚)
• 体の動きを感じる(固有受容感覚)
• バランスをとる(前庭感覚)
• においや味を感じる(嗅覚・味覚)
これらの感覚は、ただ「受け取る」だけでなく、「うまくまとめて使う」ことが大切になります。
この「まとめて使う」ことを《感覚統合》と言います。
感覚統合は、子どもにとっての「土台」作りを促進してくれる
感覚統合がうまくいっている子どもは、自分の体を思い通りに動かせたり、音や光に過敏にならずに集中できたりします。
つまり、学習・運動・お友達との関わりなど、「できる!」のいろんな場面の土台になっているのです。
逆に、感覚統合がうまくいかないとこんな様子が見られることも:
• 服のタグや靴下の感触をいやがる(触覚の過敏)
• 音にすごく敏感で、すぐに疲れてしまう(聴覚の過敏)
• じっと座っていられない(前庭・固有感覚の調整の難しさ)
• 自分の力加減がわからず、ドン!とぶつかる(固有感覚の調整)
こうした子どもたちに、「がんばって!」と言っても、感覚の土台が整っていなければ難しいのです。
おうちでもできる感覚統合のサポート
感覚統合という言葉こそ難しいですが、内容は普段よくしていることが多いんです。考え方さえ知れば、おうちでも意識して取り入れることができます。
たとえば:
• お砂場遊びや粘土遊び(触覚)
• ブランコやジャンプ(前庭感覚)
• お手伝いで重たいものを運ぶ(固有感覚)
• お風呂で泡をなでたり、タオルで体をなでたり(触覚と安心感)
遊びの中で自然と感覚を育てていくことが、感覚統合の第一歩になります。
まとめ
感覚統合とは、「五感」や「体の感覚」をうまく整理して使えるようになること。
それが子どもたちの「できる!」を引き出す、大切な土台になっています。
「なんだかうまくいかないな」と感じたら、「がんばり方がわからない」だけかもしれません。
そんなときは、子どもを責めるのではなく、「この子の感覚はどう感じてるのかな?」と一歩近づいてみてください。