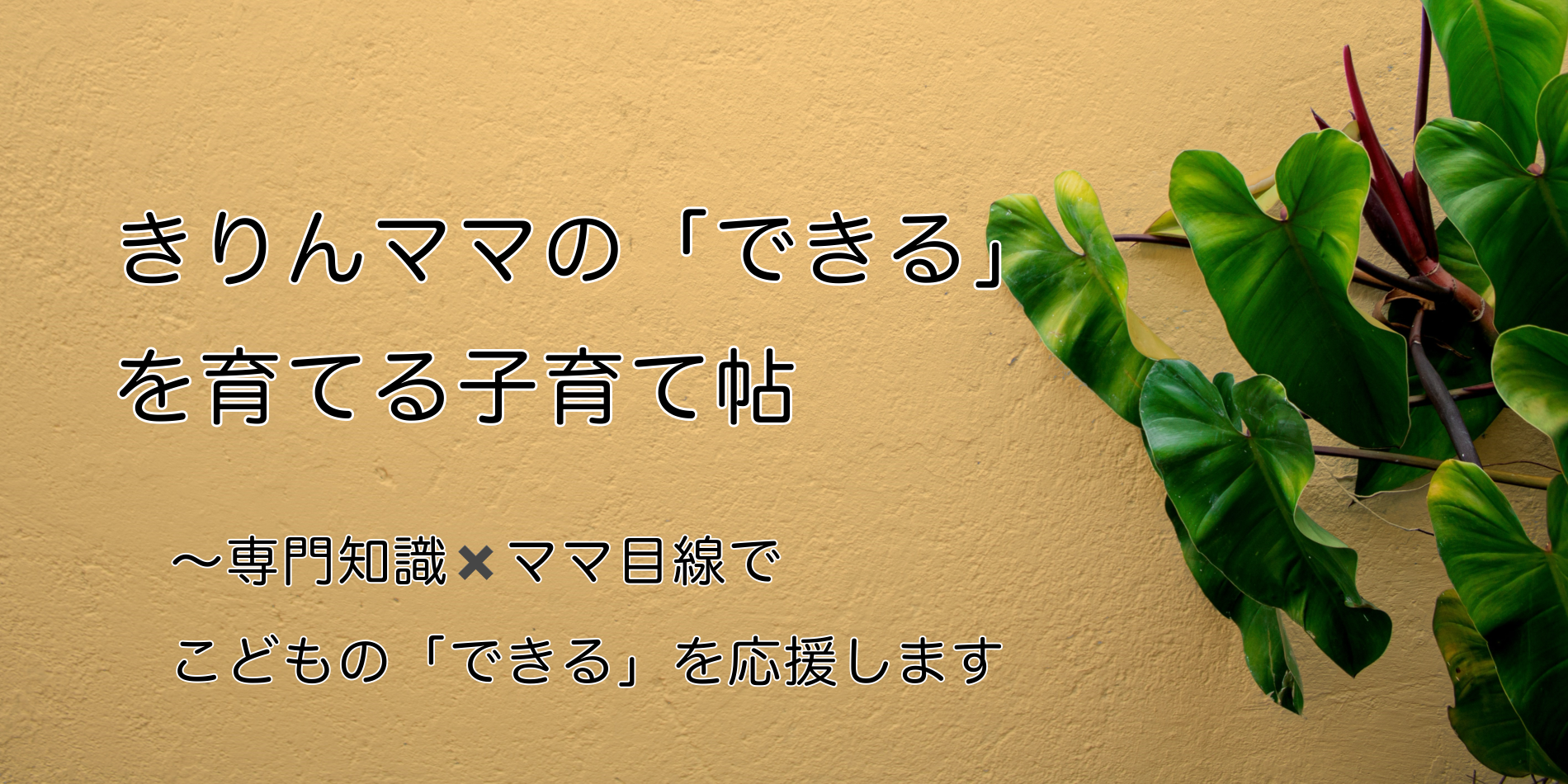「気になる」から「知る」ことで、できるを育てる第一歩
「発達障害かもしれません」「グレーゾーンですね」
こんな言葉をお子さんについて聞いた時、多くのママ・パパは、驚きや不安、そして戸惑いで胸がいっぱいになります。
「私の育て方が悪かったの?」「うちの子に障害があるってこと?」
そんな風に自分を責めてしまう方もいるかもしれません。
でもまず最初に伝えたいのは「親のせい」ではないこと。
そして、「診断」はレッテルを貼るためのものではなく、「その子に合った支援を始めるスタートライン」なのです。わが子の傾向を「知る」だけでも子供の成長に大きなプラスです。
発達特性ってどんなもの?
発達特性とは、生まれつき脳の発達の仕方に特性があり、成長の中で「ことば」「運動」「対人関係」「感情のコントロール」などが周囲と比べて少し違って見える状態のことです。よく知られているものには以下のようなタイプがあります。
• 自閉スペクトラム症(ASD)
→ コミュニケーションが苦手、こだわりが強い、感覚の過敏がある など
• 注意欠如・多動症(ADHD)
→ 集中が難しい、じっとしていられない、順番を待つのが苦手 など
• 学習障害(LD)
→ 読む・書く・計算するなど、特定の分野の学びに困難がある など
このように、発達特性にはさまざまなタイプがあり、子ども一人ひとりに異なる「得意・不得意」があります。これは発達特性のある、なしに関わらず、みんなあります。「何が得意で、何が苦手なのか」を知ることがとても大切になります。
「グレーゾーン」って?
「グレーゾーン」とは、発達の特性があるけれど、診断の基準には完全には当てはまらない状態のことです。よって、もちろん医学的な診断ではありません。
たとえば、
• 困りごとはあるけれど、園や学校ではなんとか過ごせている
• 特定の場面ではうまくいくけれど、家庭では大変なことが多い
• 「診断を受けるほどではないけれど、育てにくさがある」
そんな子どもたちが、「グレーゾーン」と呼ばれることがあります。
この「グレー」という表現が、余計に不安を強めてしまうこともありますが、見方を変えると、
「どんな配慮や関わり方があれば、その子が力を発揮できるのかを一緒に探す」というスタンスで接することができる、とも言えるのです。
診断=レッテルではない
診断がつくことに対して、「この子に障害があると決めつけられるのでは…」と心配になるのは自然なことです。
でも、診断とは「子どもの困りごとの理由を明確にするための手がかり」であり、その子に合った支援や関わり方を見つけていくための“地図”のようなものです。
たとえば、
• 「この子には、言葉での指示よりも、視覚的な説明の方が伝わりやすいんだな」
• 「急な変化が苦手だから、見通しをもって動けるようにしよう」
• 「じっとするのが苦手だから、活動に“動き”を取り入れていこう」
など、その子の“特性”を理解し、その子が安心して生活できる環境を整えることができます。
子どもたちは“困っている”だけで、“困らせたい”のではない
「ふざけてるの?」「やる気がないの?」と思ってしまう行動も、実は子どもにとっては
「どうしたらいいかわからない」「頑張ってもうまくいかない」サインかもしれません。
そう思ったときに、
• 「何がこの子を困らせているんだろう?」
• 「どんな手助けがあれば、できるようになるかな?」
と考えてみると、子どもとの関わり方が少しずつ変わってくるかもしれません。
「できる」を育てるために大切なこと
発達特性はその子の「個性の一部」です。
「個性」は、正しく理解され、丁寧に育まれていくことで、大きな強みにもなっていきます。
大切なのは、「この子はどんな子?」「どうしたら安心して育っていける?」を、考えることです。
わが子のために情報を探して勉強しているあなたはきっと大丈夫。
その子の“らしさ”を大切にしながら、「できる」をひとつひとつ増やしていく毎日を応援しています。