春休み、夏休み、冬休みなどの「長期休み」。学校という「決まったスケジュール」がなくなるこの期間、発達障害のある子どもたちにとっては、意外にも過ごしにくい時間になることがあります。今回は、そんな長期休みを「少しでも安心して」「有意義に」過ごせる工夫を、丁寧にお伝えします。
「毎日同じ流れ」を意識してスケジュールを立てよう
発達障害の子は、「見通しが立たない状況」が苦手なことが多いです。
急な変更や、予定がないことで不安になったり、パニックになったりすることもあります。
対応のコツ:
• 朝起きる時間、食事、勉強や遊びの時間などを「ざっくり」でも決めて、毎日ほぼ同じ流れで過ごせるようにしましょう。
• ホワイトボードやカレンダーに予定を書き、子どもと一緒に確認します。
• 絵やイラストで視覚的に示すと、理解しやすくなります。
「外出ゼロ」は避けよう。環境の変化が脳への刺激に
長期休みにずっと家にいると、生活が単調になり、気持ちが不安定になることもあります。
外の世界に触れることで、気分転換にもなり、感覚の刺激にもつながります。
対応のコツ:
• 公園に行く、スーパーに一緒に買い物に行く、図書館に行くなど、日常的な外出を1日1回取り入れてみましょう。
• 人混みが苦手な子には、時間帯を工夫(午前中の早い時間など)するだけで、ずっと安心して外出できます。
遊びは「本人の得意」を伸ばすチャンス!
長期休みは、勉強だけでなく「遊びを通じた成長」にもピッタリの時間。
ASD(自閉スペクトラム症)やADHDの子は、興味のあることに集中できる力があります。
対応のコツ:
• 工作やレゴ、パズル、プログラミングおもちゃなど、「好きなこと」を思い切りやらせてあげましょう。
• ADHDの子は体を動かす遊び(トランポリン・サーキット遊びなど)で、エネルギーを発散させると落ち着きやすくなります。
勉強は「量より習慣づけ」を大切に
長期休みになると、学習のペースが乱れがち。でも、無理にたくさんやらせると逆効果になることも。
対応のコツ:
• 毎日10分だけでもいいので、勉強の時間を「決まった時間に」「短く」設定。
• タブレット学習や音読、計算カードなど、子どもが好きな方法で続けられる工夫を。
「疲れすぎ」に注意!休みの日こそ“何もしない日”を
普段と違うスケジュールに子ども自身が疲れやすくなるのが、長期休みの落とし穴。
おでかけやイベントを詰め込みすぎず、意識して「ゆっくりする日」を作ってあげましょう。
対応のコツ:
• 親子でゴロゴロする日、ゲームや動画を一緒に楽しむ日など「心を緩める時間」を大切に。
• 「何もしない=悪いこと」ではありません。回復のための大事な時間です。
おうちの人もがんばりすぎないで
長期休みは親も大変。「毎日イライラしてしまう…」そんな声も少なくありません。
対応のコツ:
• 子どもが夢中になっている間に、親もコーヒータイムを。短い時間でも「自分の時間」を意識的に取ることが大切です。
• 「できなかったこと」より、「できたこと」「今日はがんばったこと」を一緒に振り返って、小さな成功体験を大切に。
まとめ
長期休みは、ペースが崩れやすい時期。でもちょっとした工夫で、「安心」と「成長」を支えられる大切な時間に変わります。
無理のない範囲で、お子さんに合ったリズムを一緒に見つけていけたらいいですね。
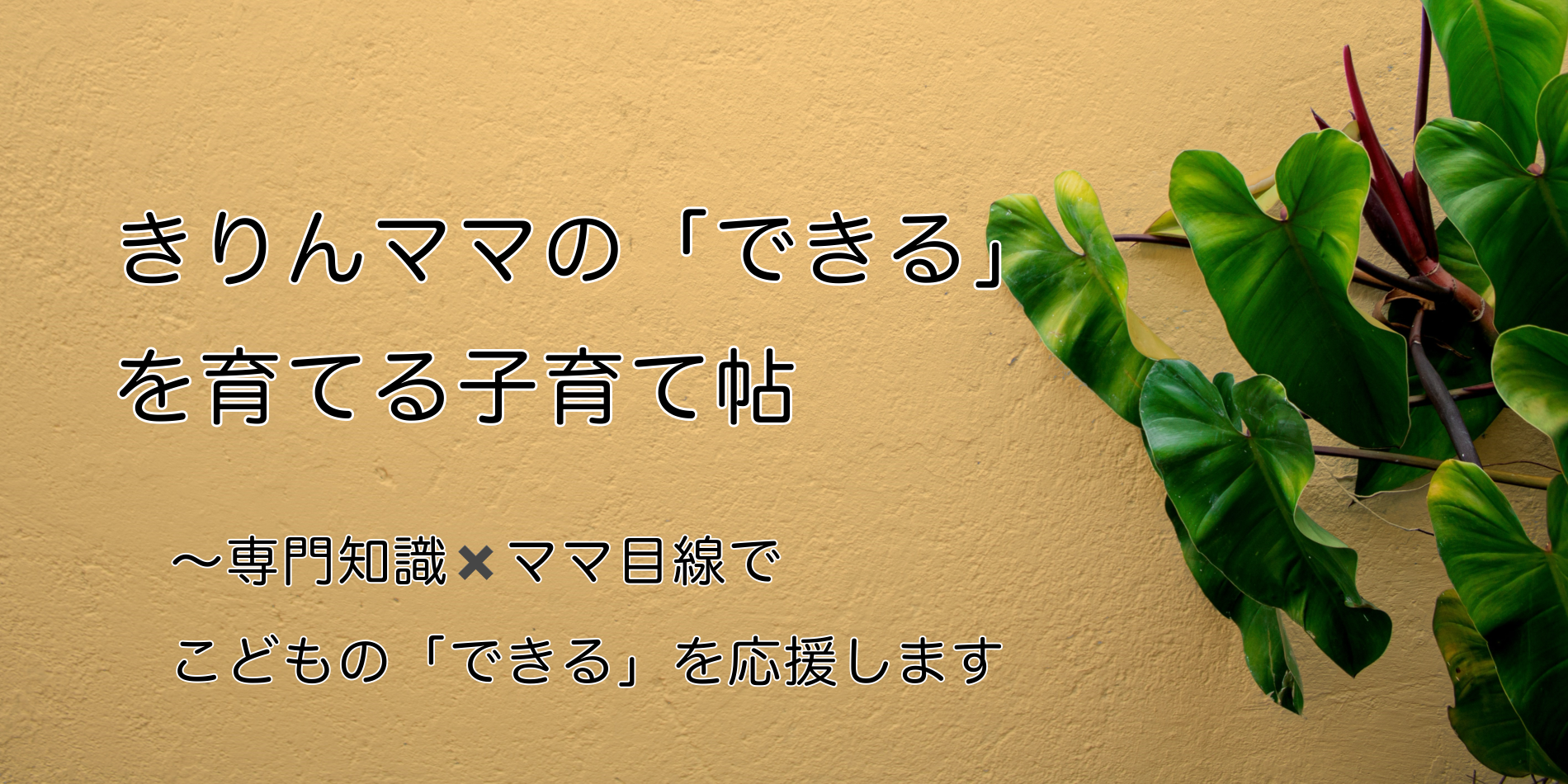


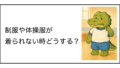
コメント