保育園や幼稚園と違い、小学生になると始まるのが「宿題」ですよね。
発達特性がある、またはグレーゾーンと呼ばれる子どもたちは、宿題に取り組むことにさまざまな困難を感じることがあります。
でも、それは「やる気がない」「さぼっている」からではありません。
子どもの感じている「むずかしさ」を丁寧に見つけて、できるところから一緒に取り組んでいくことが大切です。ここでは、そんな子どもたちと宿題に向き合うための工夫や、周囲の関わり方を紹介します。
宿題量の調整の目安
「これだけでいいの?」と思うくらいが、ちょうどいいスタートライン
子どもにとって「量が多すぎる宿題」は、それだけでやる気をなくしてしまいます。
特に発達障害がある子どもは、「見通しを立てる」「集中を持続する」ことが苦手なことも多く、1ページ分でも圧倒されてしまうことがあります。
調整のコツ:
• 1回の宿題は「10分以内」で終わる量に
→ 集中が続く時間に合わせて設定しましょう。
• 問題を全部やらなくてもOK!
→ 例:計算ドリルの半分だけ、1問おきに解くなど。
• 本人と一緒に「どれだけやるか」を決める
→ 子どもに「自分で決めた感」があると、意欲につながります。
🔸 先生に「うちの子は集中力が続きにくいので、まずは量を減らして慣らしていきたい」と相談しておくのもおすすめです。
取り組み方の工夫
子どもの「特性」に合ったやり方で!少し工夫してその子に合った方法にカスタマイズしてみましょう。
取り組み方の工夫例:
• 書くことが苦手な子
→ 口頭で答えを言って、それを大人が代筆してあげる
→ タブレット学習で代替する
• 集中が続かない子
→ タイマーを使って「5分やったら1分休憩」など、短時間集中法を使う
→ 宿題を細かく分けて「できた感」を積み重ねる
• やる気が出ない子
→ 宿題前に体を動かす時間を設ける
→ 宿題が終わったら好きな活動ができる「ごほうびタイム」を設定する
援助者の姿勢
「やらせる」より「一緒に取り組む」姿勢を大切に
子どもが宿題でつまずいていると、「ちゃんとやりなさい!」「早くやりなさい!」と声を荒げてしまいがちです。でも、そうすると子どもは余計に苦しくなります。
親の関わりのポイント:
• 子どもと「同じチーム」になる
→ 「今日はどれやる?」「これは難しいね、どうしようか?」と、一緒に考える姿勢を。
• できたらしっかりほめる!
→ 1問でもできたら、「すごい!やったね!」と成功体験を積ませましょう。
• 叱らず、比べず、焦らず
→ 他の子と比べて「なんでできないの」と言うと、子どもの心に傷が残ります。
🌱 宿題は「できるようになること」より「親に認められること」が嬉しい体験になると、自然と意欲が育ちます。介入が必要ない場合でも、親が隣で親自身の勉強をしている環境を意識するのも取り組みがスムーズになりおススメです。
学校の先生との連携の取り方
一人で抱え込まず、相談してOK!宿題で困っているときは、無理に家で頑張らせて親子関係を悪化させるより、学校の先生に相談することが大切です。みんなと必ず同じ方法で!と求められることは減りつつありますので、焦らず子供のペースで進めていけるといいですね!
相談のポイント:
• 「こういう特性があって、宿題にとても時間がかかってしまうことがある」
• 「家では、これくらいの量が限界のようです」→具体的に提示できればよりベター
• 「宿題の内容を簡単にしたり、やり方を変えさせてもらえませんか?」
💡担任の先生と連携して、「本人が無理なく取り組める宿題の形」を一緒に探しましょう。どうしたらよいかわからない、という場合は「困っている」という意思表示を伝えるだけでももちろんOK
通級指導や特別支援教育コーディネーターがいる学校なら、そこにもつないでもらえます。
まとめ
宿題は「できる」を育てる手段のひとつです。
宿題は「勉強を定着させるため」にありますが、それが子どもや親の負担になりすぎるのは本末転倒です。その子の発達段階や特性に合わせて「できる形」に調整することで、少しずつ「自信」と「習慣」が育ちます。
お子さんが「自分はできるんだ」と思える宿題のかたちを、少しずつ見つけていきましょうね。
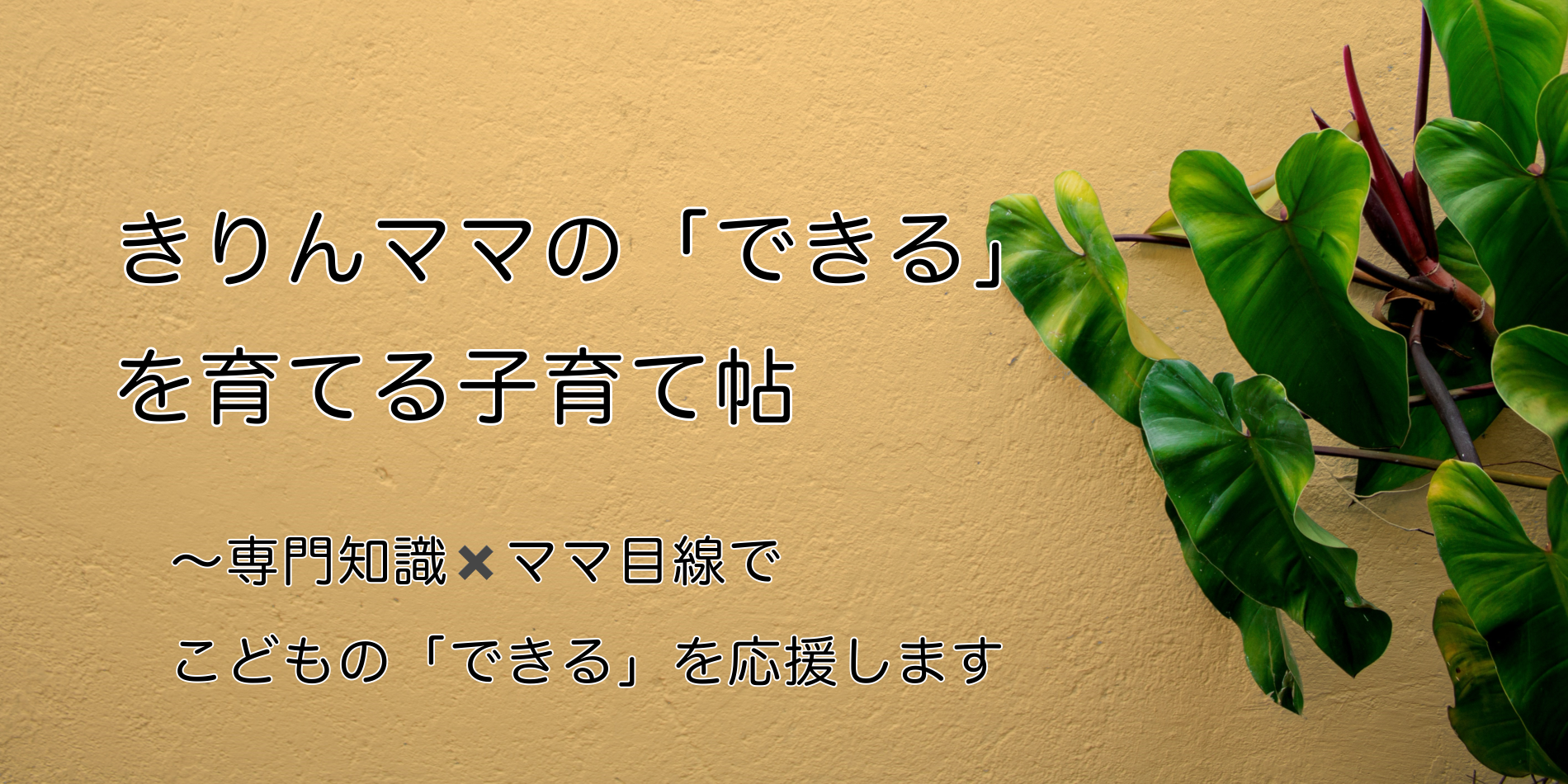
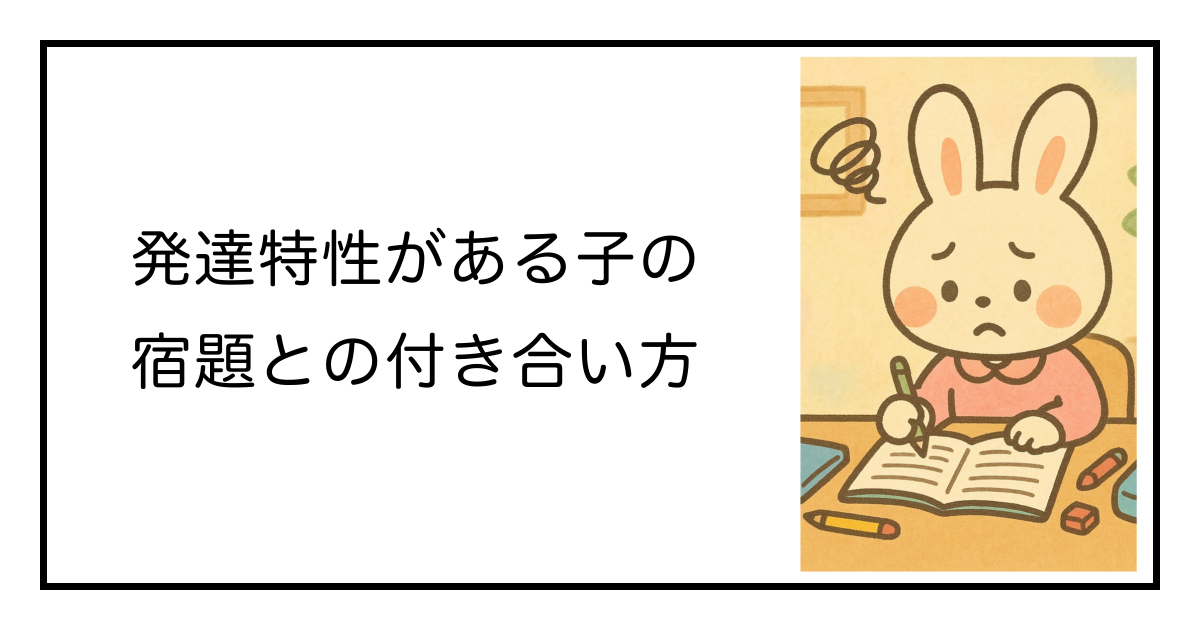
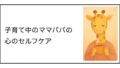
コメント