冬になると増える「だらだらモード」
寒くなると、朝起きるのがつらい・動きが鈍くなる・なんとなく元気が出ない…。
そんな「だらだらモード」は、実は多くの子どもが感じる季節的な身体の反応です。
特に発達特性のある子は、
• 体温調節が苦手
• 感覚の切り替えがゆっくり
• 睡眠リズムが乱れやすい
という特徴があり、冬の寒さや日照時間の短さによって 活動スイッチが入りにくくなる のです。
“だらだら”の裏にある体と脳の関係
発達支援の視点で見ると、冬の「だらだら」は怠けではなく、
体の感覚入力が減っているサイン とも言えます。
• 寒くて外遊びが減る
• 厚着で体の動きが制限される
• 朝の光を浴びる時間が減る
これらは、脳を活性化させる「感覚刺激(前庭覚・固有覚)」が減っている状態。
その結果、集中力が落ちたり、ぼんやりしやすくなるのです。
作業療法的アプローチで“動きたい体”を取り戻そう
作業療法の考え方では、「体を通して脳を整える」ことを大切にします。
冬の“だらだらモード”を改善するには、体を動かすリズムを毎日の生活に取り戻すことがポイントです。
🌞 朝のおすすめルーティン
- カーテンを開けて日光を浴びる(体内時計リセット)
- 軽いストレッチ・ジャンプで体を温める
- ランドセルや荷物を自分で持つ(固有感覚を刺激)
🏠 家の中でできる運動あそび
• クッション山(ふとん山)を登る(体幹+バランスあそび)
• バスタオル綱引き(腕と背中の感覚刺激)
• 段ボール押しレース(固有感覚・全身の連動)
少し体を動かすだけで、脳への刺激が増え、集中や意欲が戻ってきます。
まとめ
「冬になるとだらだらする」は、子どものせいではなく、体の感覚が冬仕様になっているだけ。
作業療法の視点を取り入れて、
・体を動かす
・朝の光を浴びる
・リズムを整える
この3つを意識することで、少しずつ“やる気スイッチ”が戻っていきます。
おうちでできる工夫から始めて、冬の「できる」を一緒に育てていきましょう。

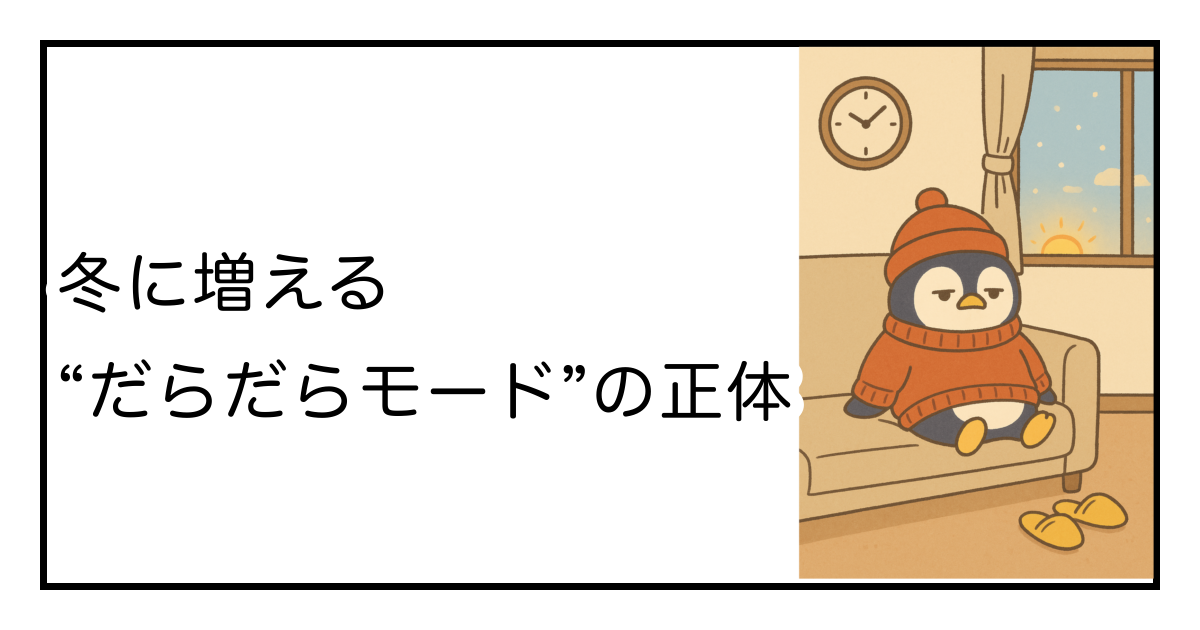
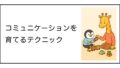

コメント