お子さんが不登校になってしまうと、親はどう対応していいか悩みますよね。このままでいいのか、どこに、もしくは誰に相談したらよいのか。お仕事をされている親御さんなら、日中家にいる子の環境はどうしてあげればよいのか、どう声を掛けたらいいのか。そんなときにできることを、たくさんご紹介していきます。
「安心できる居場所」をつくる
▷家は安全基地
学校に行けなくなった子どもは、心身にとても大きなストレスを感じています。
まずは「家は自分を責められない、安全な場所だ」と感じられるように整えることが最優先です。
具体例:
• 学校の話題を無理に出さない
• 「今日はどんな一日だった?」ではなく、「今日は何食べようか?」など日常会話を意識
• 自分の部屋やリビングなど、安心して過ごせる環境を整える
今の気持ちを受け止める努力をする
▷話す前に、聴く
こちらから話す前に、子供の話を聴く姿勢を大事にすることも大切です。きっと、子どもが不登校になった理由は一つではありません。本人も言葉にできない場合もあります。そして話すのに時間が必要になることもあります。
まずは「あなたの気持ちを大事にしたい」と伝え、無理に聞き出さずに寄り添うことが大切です。
声かけの例:
• 「言いたくなったら、いつでも聞かせてね」
• 「行きたくない理由があるんだね。教えてくれてありがとう」
生活リズムを整える・維持する
▷昼夜逆転を防ぐ
学校に行かない日が続いてくると、どうしても夜寝る時間が遅くなり、それに伴い朝がだんだん起きられなくなってくることがあります。継続的な不登校では「昼夜逆転」になってしまうお子さんはとても多いです。昼夜逆転は心と体の健康を崩す大きな原因にもなってしまいます。
まずは起床・就寝・食事の時間だけでも「おうちのリズム」をつくっていくことが回復の土台になります。
ポイント:
• 朝はカーテンを開けて日光を浴びる
• ごはんの時間は固定する
• 夜はテレビやスマホを控えめに(脳への刺激入力量を抑える目的で)
“できること”から自己肯定感を取り戻す
▷ 小さな「できたね!」を積み重ねる
不登校になると、「自分はだめだ」と思いがちな子も多いです。
でも、「朝ごはんを作ってくれた」「お皿を洗った」など、家の中でのお手伝いやお勉強、物つくりなど自宅環境でできることを一緒に見つけてほめてあげましょう。
例:
• 料理、掃除、工作など得意なことを一緒に楽しむ
• 自宅でのオンライン学習や動画学習など、興味を育てる方法を試す
学校や支援機関とつながる
▷ 一人で抱え込まない
不登校は親だけで対応するのがとても難しい問題です。不登校が継続的になると担任の先生から連絡があることがほとんどだと思います。学校の担任の先生や、スクールカウンセラー、地域の発達支援センターなど、信頼できる支援者に相談することも親の大事な役割です。一人で抱え込んでしまうと不安も大きくなってしまうので、現状を共有できる相手を親以外に見つけましょう。
連携のヒント:
• 学校に「連絡帳」や「電話」で状況を伝える
• 保健室登校や別室登校などの提案をもらう
• フリースクールや家庭訪問支援、自宅学習などの情報も検討する
将来を焦らない視点を持てるよう努力する
▷回復に時間がかかる場合もある
子どもが自分のペースで「次に進めそう」と感じるまで、焦らず待つことも大切です。言葉でいうのは簡単ですが、これは本当に難しいことです。ただ、子供の持てる力を信じて、回復を待ってあげるというのも親が寄り添ってくれている安心感につながります。
親のための心の持ち方:
• 「今は心を休める時間」だと捉える
• 他の子と比べない
• 親自身もサポートを受けてよい(カウンセリング、相談会など)
親自身のセルフケアも忘れずに
▷ 頑張るお母さん・お父さん自身のケアは子供を支える力になる
子どもが不登校になると、子供の抱える不安感に影響されますし、親自身も孤独や不安でいっぱいになります。予測できない将来への漠然とした不安を抱えてしまうのは当たり前です。
そんな時は親自身のメンタルケアがあってこそ、子どもを支える力になります。
親のためのセルフケア例:
• 一人になれる時間を意識的に作る
• 親の会やSNSなどで「同じ立場の仲間」とつながる
• カウンセラーに自分の気持ちを話してみる
支援機関の一覧
一人で抱えこまないためにも、頼れる窓口を把握しておくことはとても大切です。地域ごとに名称が異なりますが、主に以下のような機関があります。
① 学校(担任・スクールカウンセラー・特別支援コーディネーター)
• 担任の先生は、子どもの学校生活における最前線の理解者です。
• スクールカウンセラーは、心の専門家。保護者も相談OK。
• 「特別支援コーディネーター」がいる学校では、発達や支援の調整を担っています。
② 教育支援センター(適応指導教室)
• 「適応指導教室」とも呼ばれ、学校外で学べる場所。
• 少人数で活動でき、安心して通える雰囲気を持っています。
• 学校復帰が目標ですが、無理に戻さない選択もできます。
③ 児童発達支援・放課後等デイサービス
• 発達に特性のあるお子さんが通える福祉サービス。
• 個別支援計画を立てて、遊び・学び・生活の練習を支援。
• 保護者の相談も受けてくれます(利用には市区町村での手続きが必要)。
④ フリースクール・オルタナティブスクール
• 子どもの「居場所」として注目されている民間の教育機関。
• 勉強をするところもあれば、創作や体験を大切にするところも。
• 子どもの「合う場所」を探す選択肢としておすすめです。
⑤ 地域の子育て支援センター・相談機関
• 市区町村が運営する子育て支援窓口。
• 不登校だけでなく、発達や家庭の困りごとも相談できます。
• 専門職(臨床心理士、保健師など)が常駐している場合もあります。
家での声掛け集
不登校の子どもにどんな言葉をかけたらよいのか迷う親御さんへ。
以下のようなシンプルな声かけが、子どもを安心させ、心の回復を後押しします。
✅ 安心感を与える声かけ
• 「ここにいていいよ」
• 「どんな気持ちも話してくれてうれしいよ」
• 「おうちにいてくれて、ママ(パパ)は安心するよ」
✅ 自己肯定感を育てる声かけ
• 「昨日よりちょっと元気そうだね」
• 「お皿を下げてくれて助かったよ」
• 「自分の気持ちに気づけたの、すごいことだよ」
✅ 学校に無理に行かせないための声かけ
• 「行けなくても大丈夫だよ」
• 「今は休むことが大事だね」
• 「戻ることより、元気になることを考えよう」
不登校体験談
🧑🦰 保護者の体験談(仮名)
◆ ケース①:毎朝泣いていた息子(まさとくん・小2)
最初は「甘えてるのかな?」と思っていました。でも、本人は本当に苦しんでいて、毎朝お腹が痛いと泣くように…。保健室登校を数週間試したあと、教育支援センターに通うようになりました。今はフリースクールでのびのび過ごしています。「行く場所がある」ということだけで、本人の表情が全く変わりました。
⸻
◆ ケース②:優等生の長女(さきちゃん・小5)が突然の不登校
突然「もう学校に行きたくない」と泣いてしまいました。理由は、「自分の理想通りに勉強ができないことが苦しい」とのこと。親としては驚きましたが、話を聴くうちに、プレッシャーをかけすぎていたことに気づきました。今は家庭教師に見てもらいながら、自宅で学び直しています。焦らない、比べないが合言葉です。
⸻
◆ ケース③:発達特性のある弟の影で、頑張ってきた長男(けんたくん・小4)
兄弟のサポートに追われて、長男の変化に気付けていませんでした。学校での孤立感があったようで、家でも無表情が増え…。思い切って一対一で「けんたのこと、ちゃんと見てるよ」と伝えると涙がポロポロ。それがきっかけで、今は一緒に散歩に出かけたり、少しずつ自分を取り戻しています。
⸻
まとめ
不登校は、親子にとって「立ち止まり、見直すチャンス」でもあります。
「行けない」ことに目を向けるより、「今この子に必要なことはなにか?」を一緒に考えていきましょう。どうか焦らず、一緒に悩みながら、子どもの“今”を大切にしてあげてください。
おまけ
「天神」ってしってますか?「教科書準拠」で学校と同じように学習ができ、予習・復習にもピッタリです。そして、文科省の不登校児の出席扱いにも対応しているんです!中学受験など内申点対策などのために出席扱いを獲得したい子にぴったりです。日々の学習内容や学習時間などがワンタッチで出力できて、親御さんの手がかからないように工夫されています。
不登校だけど、今後のために内心点対策はしておきたい!中学受験の選択肢を残しておきたい!という方は、資料だけでも見てみてください。

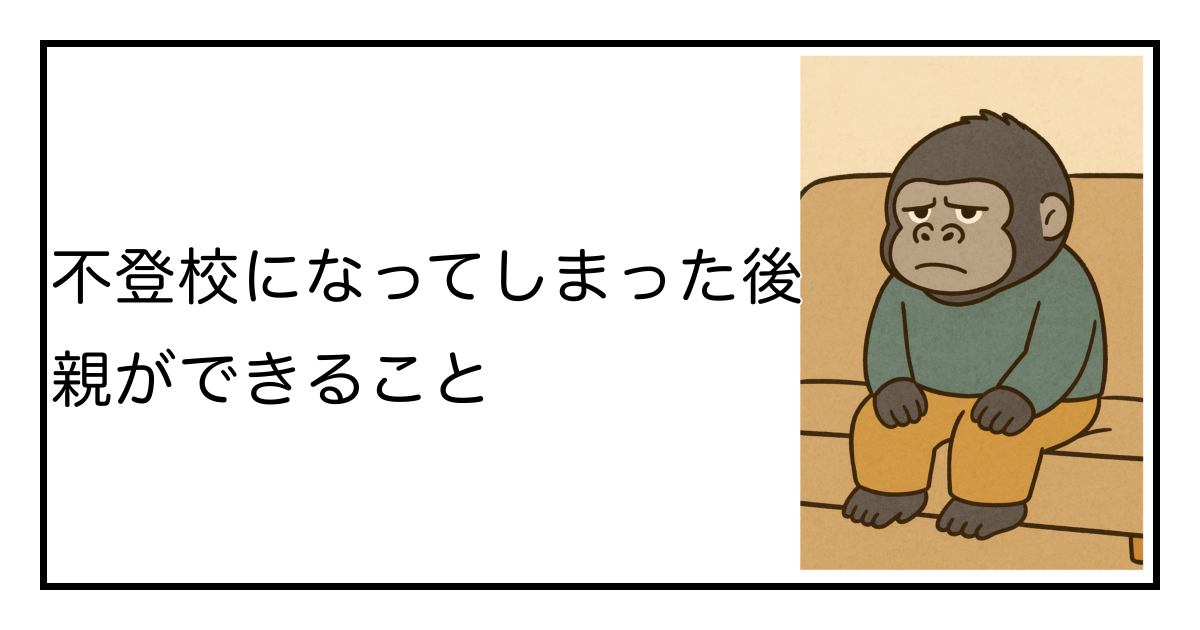
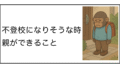
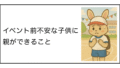
コメント