ASD(自閉スペクトラム症)の子が伸びる勉強方法とは?
ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんは、得意・不得意がはっきりしていることが多く、興味のあることに深く集中できる一方で、抽象的な指示や感覚刺激には困難を感じることがあります。けれども、「合った方法」で学べば、ぐんぐん伸びる子がたくさんいます。
ここでは、ご家庭でできる支援の工夫を紹介します。
こだわりのあるものを「とことん尊重」
ASDの子は、一度興味を持ったものに強く集中できる「こだわりの強さ」が特徴的。そのこだわりを「勉強の入り口」に使うのが効果的です。
例:
• 電車が大好き → 路線図を使って地理や算数(距離・時刻)を学ぶ
• 恐竜が好き → 恐竜図鑑でひらがな・カタカナを覚える
「好き」なものは集中力と記憶力を引き出してくれる強い味方になります。好きなキャラクターの問題集を選んでもらうのもいいですね。
 | ポケモンずかんドリル 小学1年生 すう・ずけい・たんい (知育ドリル) [ 矢部 一夫 ] 価格:1078円 |
 | すみっコぐらし小学1・2年のたんい・ずけい総復習ドリル/卯月啓子【3000円以上送料無料】 価格:1100円 |
目で見てわかる教材を使う
ASDの子は「耳からの情報」より「視覚情報」の方が理解しやすいことが多いです。以下の工夫が効果的です。
おすすめの工夫:
• 絵や図、写真が多い教科書、タブレットを使う
• 書く量を減らして、マークや線で答えられるプリントを使う
• ホワイトボードや付箋で指示を整理する
耳で聞く説明より、「見てわかる工夫」を取り入れると、理解度がぐんと上がります。
スモールステップで「できた!」を増やす
ASDの子は、「先が読めない不安」や「大きすぎる課題」に不安を感じやすい傾向があります。そこで、1つの課題を細かく分けてあげると安心して取り組めます。
例:プリント1枚の宿題でも…
• 「今日は5問だけやってみよう。明日また5問やってみよう」
• 「最初の2行だけ読もう」
できたら大げさなくらいほめてあげて、「自信の貯金」をしていきます。
勉強をパターン化する
「学校から帰ったら、勉強机で10分勉強する」といったように、勉強する時間や場所をパターン化すると混乱を減らすことができ、スムーズに取り組めます。
勉強する「場所」と「時間」を整える
ASDの子は感覚に敏感な場合も多く、周囲の音や光、ざわざわした環境が気になって集中できないことがあります。
工夫できるポイント:
- 静かで落ち着ける場所を選ぶ(リビング学習より個室、壁際など情報量を少なくする)
- 1回の勉強は10~15分程度にして、こまめに休憩をはさむ
- 机の上は、勉強するもの以外何も出さない
復習より予習
ASD(自閉スペクトラム症)の子は、新しい情報や変化に敏感なため、自宅であらかじめ授業内容に触れておくと、学校の授業での入力がスムーズです。本人も軽く内容をしているだけでも、不安感すくなく授業に取り組むことができます。
まとめ
安心できる環境設定と明確な見通し、教材選びで学びの力をどんどん引き出しましょう。
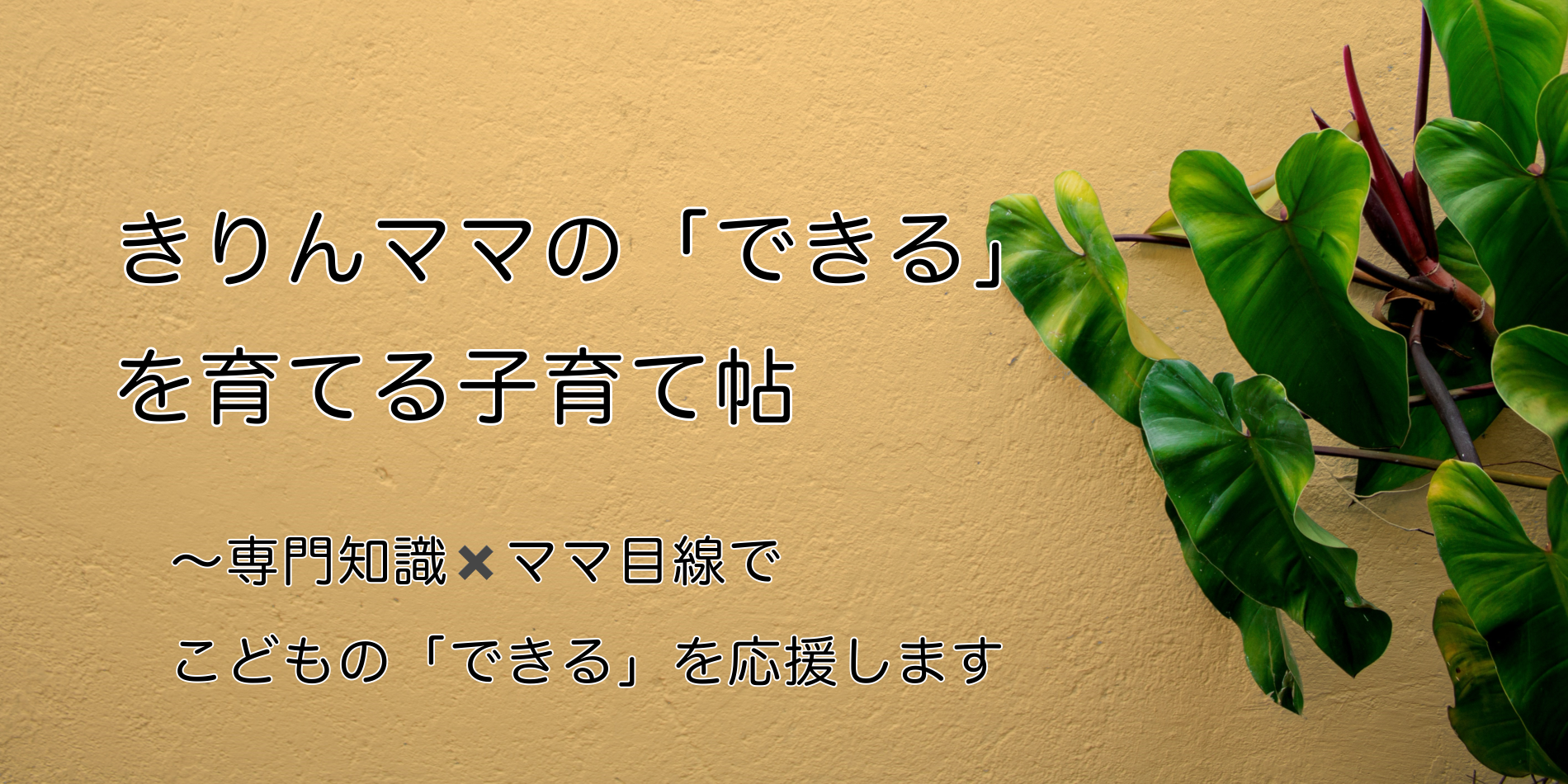


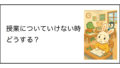

コメント