小学校になっても夜尿(おねしょ)が続くと、親として心配になったり、「いつまで続くんだろう」「このままで大丈夫なのかな」と不安になったりしますよね。子ども自身も、友達とのお泊まりや修学旅行を前に、不安や恥ずかしさを抱えていることが少なくありません。
今回は、夜尿症にどう向き合えばよいのか、医療的な視点も交えながら、家庭でできる対応をご紹介します。
夜尿症とは?
5歳を過ぎても月に数回以上の頻度でおねしょが続く状態を「夜尿症」と呼びます。実は小学校低学年では10人に1人ほどの割合で見られ、小学校高学年でも5%前後の子どもに見られる、決して珍しくないものです。
夜尿症は、「親のしつけの問題」でも「子どもの甘え」でもありません。医学的には以下の3つが主な原因とされています:
• 膀胱の容量が小さい
• 夜間の尿量が多い
• 睡眠中に尿意で目覚めにくい
対応法4選
① 叱らず、プレッシャーを与えないこと
まず最も大切なのは、「絶対に叱らない」こと。
夜尿は本人の意思でコントロールできるものではありません。にもかかわらず、繰り返すことで自己肯定感が下がりやすく、「また失敗しちゃった…」という気持ちがストレスを生みます。
「大丈夫よ」「失敗しても平気だよ」という温かい言葉が、子どもの心を守ります。
② 睡眠リズムと生活習慣の見直し
生活リズムを整えることは、夜尿の改善にもつながります。
• 寝る直前の大量の水分は避ける(2時間前までが目安)
• 寝る前にしっかりトイレに行く習慣をつける
• 適度な運動をして深い睡眠を得る
• 寝る時間を毎日同じにして、体のリズムを整える
また、便秘も膀胱を圧迫し、夜尿の原因になることがあります。食物繊維や水分をとり、便通を整えることも大切です。
③ 医療機関に相談するタイミング
「もうすぐ修学旅行…」「お泊まり行事が不安」
そんな時は、できればイベントの3〜6ヶ月前に小児科・泌尿器科などの医療機関に相談を始めておくのがおすすめです。
治療には時間がかかる場合もありますが、以下のような選択肢があることを知っておくと安心です。
• 夜尿症用の薬の使用(抗利尿ホルモン薬など)
• アラーム療法(濡れると音が鳴る装置で排尿を意識づける)
• 排尿日誌による記録と傾向の把握
※治療がすぐに効果を出すとは限りませんが、「取り組んでいる」という気持ち自体が、子どもに安心感を与えることも多いです。
④ 子どもと一緒に「できていること」に目を向けて
夜尿以外の面で、「早起きできたね」「朝ごはんしっかり食べたね」「友達と仲良くできたね」など、日々の小さな成功体験に注目し、子どもの自信を育てていきましょう。
夜尿症があると、ついそこばかりに目が行きがちですが、お子さんは毎日いろんなことをがんばっています。
まとめ
夜尿症は、子どもの成長の過程で起こる「よくあること」です。
焦らなくて大丈夫。
比べなくて大丈夫。
治療法もありますし、多くの場合、成長とともに改善していきます。
大切なのは、「あなたをそのまま受け入れているよ」というメッセージを、子どもに伝え続けることです。
どうか、子どもと一緒に、安心してこの時期を乗り越えていけますように。

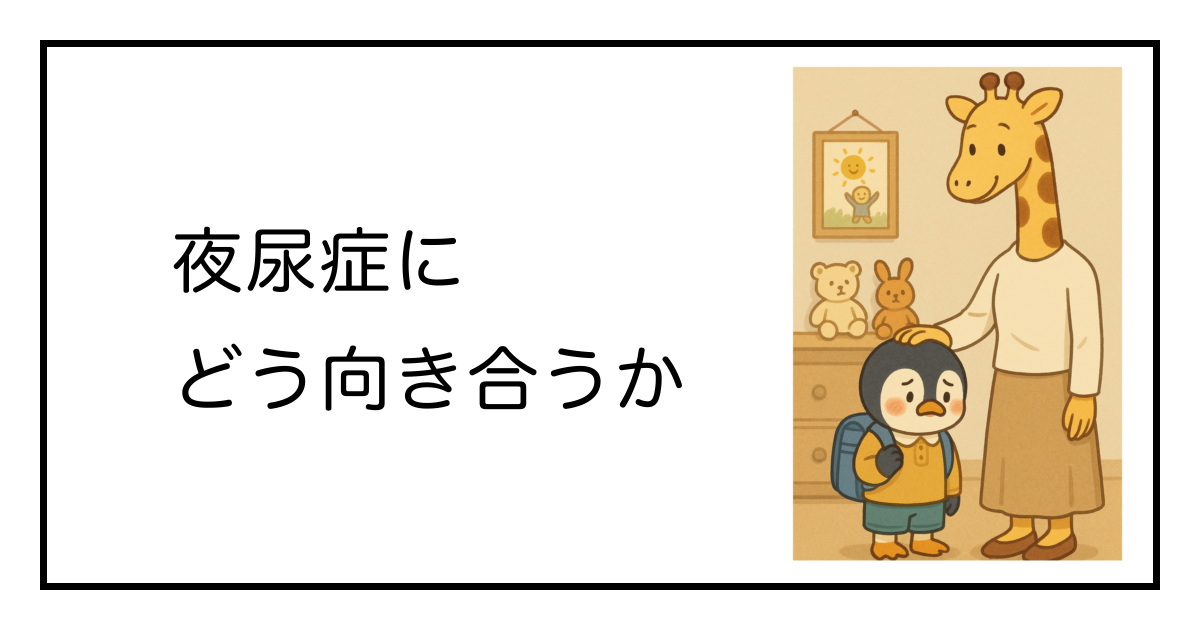
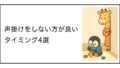
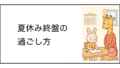
コメント