「うちの子、癇癪がひどくて…」なんて相談、よく聞きませんか?
最近、「すぐに怒る」「思い通りにならないと泣きわめく」「叩いたり、物を投げたりしてしまう」といった、感情のコントロールが難しい子どもが増えていると感じます。
実際、子どもの癇癪(かんしゃく)行動が増えているという傾向は、教育・保育・医療現場でも報告されています。
例えば、国立成育医療研究センターが2021年に行った調査(※1)では、3~6歳児の保護者の約30%が、「子どもが激しい癇癪を日常的に起こしている」と回答。また、2023年の文部科学省の資料(※2)でも、感情・行動の自己調整が難しい幼児が増えていることが保育現場から報告されています。
子どもの癇癪が「育てにくさ」や「家庭のストレス」に直結している今、大人が“正しく理解し、適切に関わる”ことが何より大切です。
癇癪は「困っている」サイン
癇癪とは、子どもが自分の気持ちをうまく言葉にできずに爆発してしまう状態。
特に2~6歳ごろの子どもは、言葉も感情もまだ発展途上。言いたいことはあるけれど言葉が追いつかない、我慢したいけれど我慢の仕方がわからない、という「葛藤」の真っただ中にいます。
だからこそ、癇癪は子どものSOS。
「自分でもどうしていいかわからない!」という“混乱”の中にいるのです。
感情コントロールは「発達途中」
感情のコントロール(情動調整)は、生まれつき備わっているものではなく、経験と関わりの中で育つスキルです。
赤ちゃんの頃は泣くだけだった子が、3歳で「イヤだ!」と表現し、5歳で少し我慢できるようになるのも、すべて発達のプロセスです。
心理学ではこの力を「セルフ・レギュレーション(自己調整力)」と呼びますが、特に以下の3つが基盤になります。
- 感情に気づく力
- 言葉で表現する力
- 気持ちを落ち着かせる方法を知っていること
これらは、親や周囲の大人のかかわりによって徐々に身についていきます。決して“できない子”ではありません
子どもの感情コントロールを育てる5つのポイント
①「感情に名前をつける」習慣を
癇癪中の子どもに、「どうしたの?」「何がイヤだったの?」と聞いても、本人も説明できません。
まずは大人が感情を“翻訳”してあげることが大切です。
✅「悲しかったね」「イライラしたんだね」「不安だったんだよね」
感情に名前をつけてもらうことで、子どもは「これは“怒り”っていう気持ちなんだ」と理解し、自分の内面に少しずつ気づいていけるようになります。
② “してはいけないこと”より、“どうしたらいいか”を伝える
「叩いたらだめ!」「大きな声出さないの!」という否定だけでは、子どもはどう行動してよいかわからず、混乱します。
✅「叩きたくなったら、手はぎゅっとにぎろうね」
✅「大きな声が出ちゃいそうなときは、深呼吸しよう」
というように、行動の“代替案”を伝えると、子どもは次回から“選べる”ようになります。
③「落ち着く方法リスト」を一緒に作る
怒りや混乱のときにどうしたらいいか分からない子は、安心できる方法を事前に用意しておくことが大切です。
おすすめは「落ち着きスイッチリスト」づくりです。
| 落ち着く方法 | 子供によって効果的な例 |
|---|---|
| 深呼吸する | 息を吸って「1,2,3」を数える |
| 静かな場所に行く | テント・押し入れ・ママのそば |
| 気持ちを絵にかく | 怒った顔・泣いた顔などを自由に書く |
| 手をぎゅっと握る | 身体感覚を使ってクールダウン |
| お気に入りを触る | 毛布・ぬいぐるみなど安心グッズ |
「〇〇くんの落ち着く方法どれにしようか?」と日常的に選ばせると、子ども自身が「感情コントロール」を身に着けていきます。
④ 大人が“感情モデル”になる
親がイライラをぶつけたり、怒鳴ってばかりいると、子どもも同じように“怒りで対処する”方法を学んでしまいます。
だからこそ、親もこうつぶやいてみましょう。
✅「今ちょっとイライラしてるから、深呼吸するね」
✅「ママも怒りそうになったから、一回お水飲んでくるね」
「感情を感じてもいい、でも行動は選べる」という姿を見せることで、子どもも自然と学んでいきます。
⑤「失敗しても、やり直せる」を伝える
子どもは何度も癇癪を起こし、落ち着けず、泣いたり怒ったりを繰り返します。でも大丈夫!
そのたびに「怒っちゃっても大丈夫だよ」「次はこうしてみようね」と寄り添ってもらうことで、子どもは“感情と付き合う方法”を練習している最中です。子供はまだまだ発展途上なのです。
まとめ
感情を育てることは「生きる力」を育てることです。
癇癪は“問題行動”ではなく、成長途中の自然な現象です。
そして感情コントロールとはいいますが、感情を「我慢すること」ではなく、“自分の感情を理解し、行動を選べる力”を育てること。
感情に向き合う子育ては、時間も手間もかかるけれど、それこそが子どもにとって一生の宝物になります。
癇癪が増えている今だからこそ、家庭でできる関わり方を探し、焦らず、怒らず、一緒に“心の土台”を育てていきましょう。

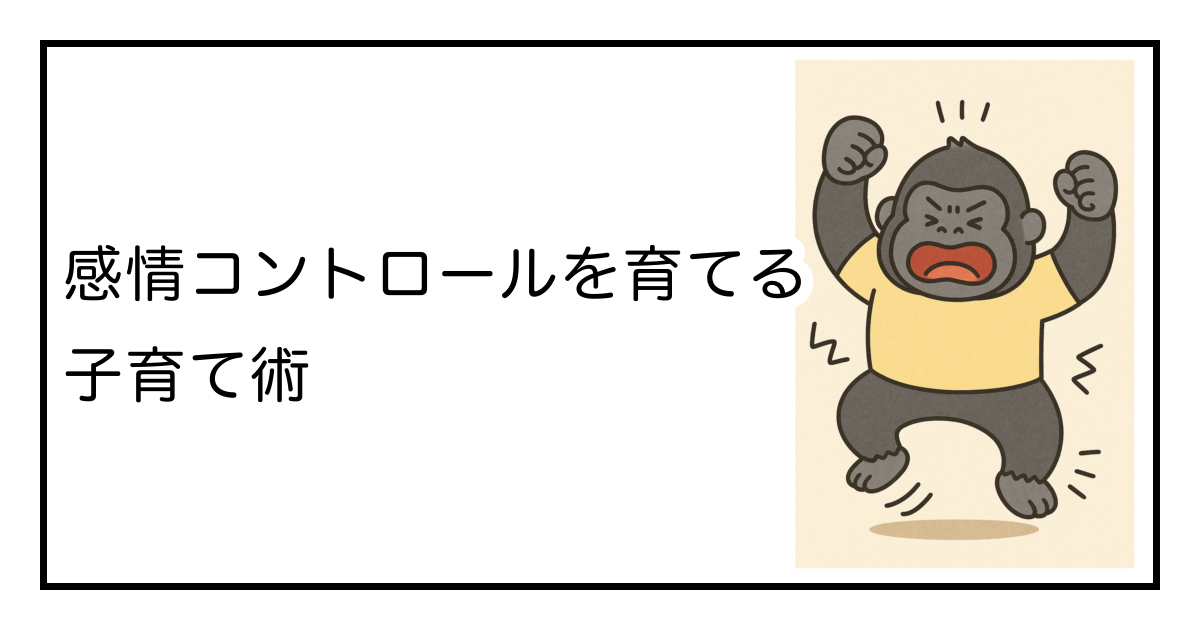
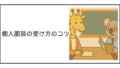

コメント