子供がひとりで遊んでいる姿を見ると、「何してるの?」「上手だね〜」「これは何かな?」と、つい声をかけたくなるのが親心。でも実は、声かけを“しない”ことが子供の発達を育てる場面があるのをご存じですか?
今回は、ひとり遊び中に“あえて”見守るべきタイミングについて、作業療法士の視点からわかりやすく解説します。
子供が集中して遊んでいるとき
おもちゃや絵本、空想遊びなどに夢中になっているときは、脳の中で創造性や集中力、自分で考える力がぐんぐん育っている時間です。
このときに話しかけると、子供の集中が途切れてしまい、「考える力」が育ちにくくなります。
✦ 見守りポイント
→ 表情が真剣・目線が定まっている・手の動きが止まらないときは、そっと見守りましょう。
試行錯誤しているとき
積み木が倒れてもまた積み上げたり、紐通しがうまくできなくても何度も挑戦したり…。そんな様子は、「できない」→「できた!」という達成感の芽生えの瞬間です。
親が先回りして「こうやったらいいよ」と声をかけると、子供の「やってみたい」を奪ってしまうことも。
✦ 見守りポイント
→ イライラしている様子がなければ、じっくり挑戦させてOK!失敗も学びのうちです。
ごっこ遊びで物語の世界に入っているとき
ぬいぐるみとおしゃべりしたり、空想の友だちと遊んでいる姿は、言葉・社会性・想像力を育てている証拠です。このときに現実の声かけをすると、せっかくの物語の世界が壊れてしまうことも。
✦ 見守りポイント
→ 独り言や人形遊びが盛り上がっているときは、遠くからそっと観察を。
イライラやトラブルが起きたとき
おもちゃが思うように動かない、パーツがはまらない…。そんな場面では、イライラしたり、手が止まることもあります。
すぐに「どうしたの?」と助けたくなりますが、まずは子供が自分で解決しようとする力に期待を。数十秒でもいいので、見守ってみてください。この繰り返しが問題解決能力を高めてくれます。
✦ 見守りポイント
→ 「困った顔」をしたときは、すぐに手助けするのではなく、「難しいね、どうしようか」と共感するだけでもOK。
まとめ
見守ること=無関心ではありません「見守る」とは、「何もしないこと」ではなく、子供の心の動きや成長のタイミングを尊重することです。
声をかけることが悪いわけではありません。ただ、タイミングを見極めることで、子供が“自分で考える力”を育てるチャンスを広げることができます。声をかけないことも、立派な関わり方ですね!

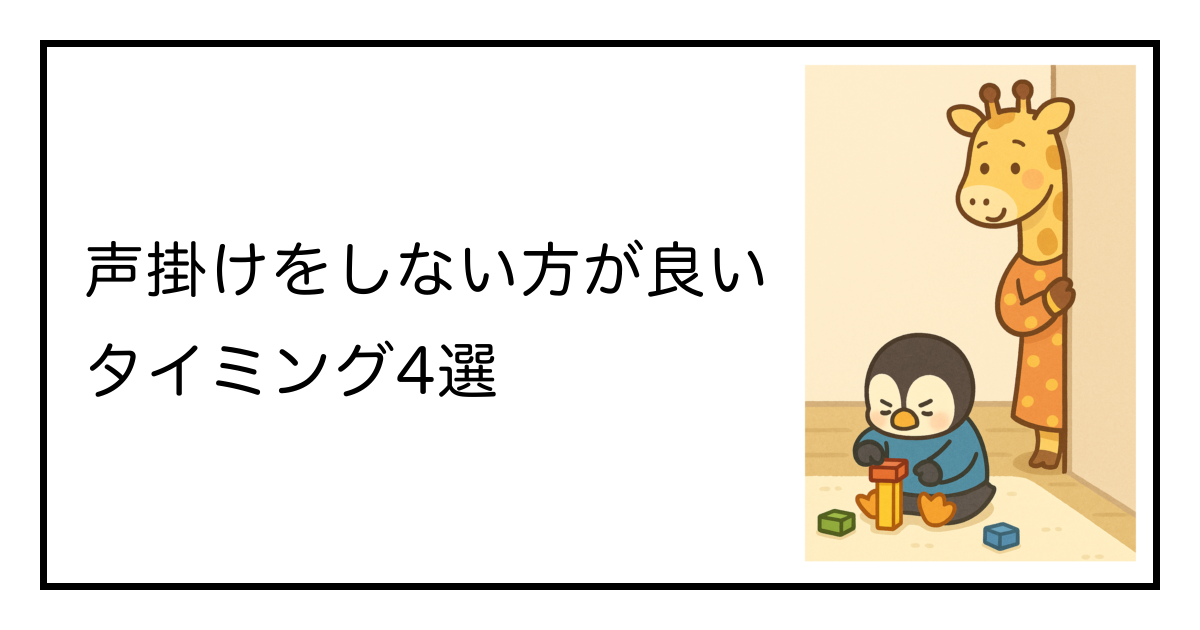

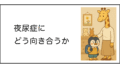
コメント